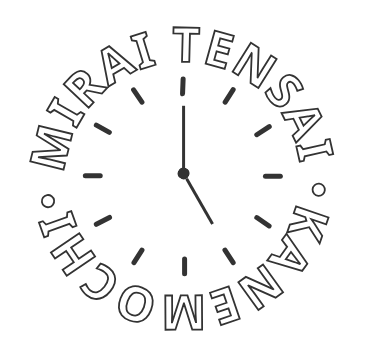中学3年生になり、定期テストの点数が内申点に影響すると知り、慌てて対策を練っているのですが、勉強がはかどりません、、
先日、このような相談を受けました。
我が息子も、中学2年生までは定期テストの点数にばらつきがあり、内申点が思わしくありませんでした。
そもそも勉強というのは、子供が勝手にするものだと思っていたので、完全に放任。
その結果、テストの順位がガクンと下がってしまい、志望校判定でC判定を食らってしまいました。

志望校に対しても、周りが言うからそこにしたというくらいで、これといって興味もなさそうでした。
そして、内申点に対するモチベーションも低く、自由時間を勉強に充てるのが嫌だという始末。

しかし、中学生男子相手に懇々と人生について語ってみても、うざがられるだけです。
あれから数か月。
試験前は、好きなゲームも封印し、もちろんYouTubeやインスタも全く観ずに、自分の時間をすべて勉強に費やし、中学3年の中間テストでは、合計点数450点以上で、平均して90点以上をとることができました。

その間に塾を変えたとか増やしたとかはなく、やったことといえば、子供への寄り添い方を変えただけです。
特に声掛けやアドバイスは、間違えてしまえば地雷を踏んでしまうようなものなので、かなり考えて使うようにしていました。
こんな方におすすめ
- 子供のやる気を引き出したい
- 志望校に合格させたい
中学受験は親のアシストが必要だということは分かるのですが、高校受験は親が口出ししても嫌がるかなと思っていました。
確かに、意味のないアドバイスはかえって逆効果。しかし、まだ自分の将来なんてよく分からないっていう中学3年生男子ですから、多少はサポートしたいものです。
子供の受験は、親と二人三脚

中学3年生ともなると、親の話は聞いてくれないわ、ウザがられるわで、進路相談の話なんてなかなかできませんよね。
私自身も、勉強に関してはあまり口を挟まずに、中学2年生までは子供に任せていました。
それが一変したのは、中学3年になって1ヶ月が経った頃です。
そういえば学級通信が毎日届いていた事に気付き、しかも内容がかなり熱くそして濃いものでした。

今までは、学校での出来事は子供任せで、学校で何が行われているのか知ろうともしていませんでした。
それが、学級通信のおかげで子供たちが今何を努力しているのか、どんな予定があるのかが把握できるようになり、子供にまかせっきりではいけないんだと思うようになりました。


学校や塾の先生が、我が子のために勉強を教えてくれたり進路指導をしてくれているのに、親の私が放任でいいのかと反省し、受験について本気で考えるようになりました。
勉強する必要性に納得できると行動につながる
難関校を目指している子は、かなり早い段階で準備をしていました。
目標が定まっているので、勉強に対するモチベーションも安定して高いです。
ちなみに我が息子ですが、実は中学3年の1学期前半くらいまでは、志望校も決まらず(興味がなく)勉強に対するモチベーションも低いまま。


将来の夢は「不労所得」とかほざいてるし、、モチベーション低すぎて爆死。
しかし、本当に将来不労所得を目指しているのなら、最速で稼いで投資して利回りを狙わなきゃいけない。
そのためには、手っ取り早く年収が高い仕事に就く必要がある、、
だから、今のうちに自分に投資して、能力を高める努力をする必要があるよね、みたいな方向にもっていったら、あっという間に志望校が決まりました。
息子の場合は、将来は好きなときに好きなだけゲームができる生活がしたいから、今勉強するという謎の理論で、突然スイッチが入ったのでした。

この勢いを無駄にしないために、ステップを踏んで、一気に学力をアップさせていきました。
勉強のモチベーションを上げる3ステップ
ここで、中学3年の中間テストでモチベーションを爆上げした、息子のやる気ステップを記載しておきます。
step
1通える範囲内にある高校で、最もレベルが高い高校を志望校にする
これは簡単にいうと「1番を目指す」ということです。
とりあえず1番を目指しておけば、後から調整がききますし、1番を目指すことで勝手にモチベーションが上がっていくからです。
今のレベルでは到底無理だと思っていても、先ずは1番を目指すことを意識してみるとよいです。
step
2得意科目を作る
この教科だけはだれにも負けない、というものを持つと、自然と他の教科も引き上げられていきます。
勉強をしたら点数が上がるということを体験する中で、やればできるかもと自信がわいてきます。
苦手科目を克服するよりも、得意教科の点数を上げるほうが簡単なので、手っ取り早く自信をつけるにはもってこいです。
step
3同じ志望校を狙っている人を観察する
自分と同じ志望校の人はどのくらいのレベルの人なのか、そしてどれくらい勉強しているのかを目の当たりにすることで、自分の勉強量が少ないということに気付けるからです。
あの人にできるのなら、自分にだってできるかもと思えたら、しめたもの。勉強量さえ増やせたら、学力は確実に上がっていきます。
モチベーションを保ち続けるために心がけたこと

モチベーションを上げるのは意外と簡単なのですが、それを維持するのは本当に難しいと実感しています。
息子の場合もかなり波がありましたし、今でもちょっとしたことで他のことに流され勉強から逃げてしまうこともたくさんあります。
しかしその度に「勉強しないの?」と聞くのも嫌ですし、それが地雷を踏むことにもなりかねません。
ですので、子供が勉強から遠のいているなと感じた時にやっていたことをお伝えします。
子供と想いを共有する
志望校を決めたものの、あまりにもレベルが高いと、やっぱり自分には難しいかもしれないと思うことも多いです。
不安だからその不安を埋めるために勉強をするというタイプなら良いのですが、せっかく頑張ったのに結果が出ないのなら最初からやらないほうがよかったと思うタイプの場合(息子のような)、ちょっとしたことでモチベーションが下がってしまいます。
特に男子は、すぐに調子に乗れるのですが、下がるのも早いです。

このようなときに、「他の人はもっと努力しているよ」などと正当論を語ってはいけません。

確かにその通りでごもっともな意見ですが、それを言っても何の解決にもならないどころか、マイナスにしかなりません。
私自身が過去に息子の地雷を踏み続けて、得た教訓です。
もっとやらなければいけなかったということは、本人が一番よくわかっているからです。

地雷踏んで自爆したくないわ。
子供が落ち込んでいたり、悔しい思いをしているときは、私も同じ気持ちを味わっていました。
全力で悔しがったり、子供の気持ちを代弁したり。
すると、子供も少しずつ落ち着いてくるというか、「今度はこうしていこう」というような前向きな気持ちに切り替わっていくから不思議です。
せっかく頑張ったのに結果が出なかったら、誰でも悔しいはず。
そのようなときは、改善方法を知りたいわけではなく、ただ気持ちを分かってほしいんですよね。
ですので、親子で思いっきり悔しがった後に、じゃあ次はこうしていこうというように、改善策を見つけていきました。
とはいえ、本気で頑張ったのに上手くいかなかったとき、そこから気持ちを切り替えるのはなかなか難しいことだと思います。
息子も「やったって無駄だったら、やる必要なんてないじゃん!時間の無駄だった。」と、よくやさぐれてましたわ。
このようなときに、以前は改善策を考えてアドバイスをしたりしていたのですが、これは全く効果がありませんでした。
素敵な思い込みを活用する
そんな時、ふと思い出したことがありました。
息子がまだ1歳か2歳ころだったか、車のナンバープレートに書いてある文字を聞いてくるので、毎回教えていたんですよ。
そしたらいつの間にかひらがなを勝手に読めるようになったことを。
たまたま興味があっただけなんでしょうが、ちょっと大げさに話してみたんです。

すると息子もまんざらではなさそうで、「あぁ、やっぱり俺って小さい時から出来るんだー」と言い出したのです。
小さい時から自分は天才だ、ということは今も天才だ。
みたいに、勝手に解釈し始め、今回できなかったのはやり方が間違っていたからだと思うようになりました。
変におだててるわけでもないので、やらされている感もなく、勝手に自分で解釈しているため効果は絶大です。
なんなら、昔は天才だったのに今できないただの凡人なんて勿体ないとまで思うようになり、「自分は天才」だからできるはずだと思うようになりました。

「誰だってやればできる」と言われても、ここまでは効果はなかったと思います。
しかし、もともと持っている能力を使うだけだと思えたら、なんだかいけそうだと思えるのかもしれません。
どうしても勉強したがらない時
もうすぐ定期テストが近づいているのに、勉強をしている様子もなく、ゲームやYouTubeばかり見ている姿を見ると、つい「勉強は?」と言いたくなってしまうものです。
こういう時に、勉強を始めるきっかけとなる声掛けは、ぶっちゃけありません。
実は子ども自身も、そろそろ勉強しなきゃやばいとは思っています。
ですが、あまりにも膨大な勉強量に、気持ちが萎えてしまっているという状態です。


そんなのわかってるし、と言われるのがおちなので、私は勉強するきっかけ作りに一緒に勉強することにしました。
子供の気持ちに全力で寄り添うためには、子供が今何につまずいているのかを知る必要があります。
国語がどうしても苦手だというのであれば、一度どんな問題を解いているのか我々も試しに解いてみましょう。
息子の場合は、どうしても国語の点数が取れず、いつも足を引っ張っていました。
本人も国語に関しては、どうやって勉強をしたら分からないといった様子で、諦め気味。
そこで、私も問題を解いてみたところ、なかなか難しかったんですよね。
子供が勉強をしたがらない理由の一つに「理解できない」というのがあります。
ですので国語は私が先に問題を解いて理解し、子供に説明できるようにしてみました。
子供の苦手強化だけでもいいので、分からないところがあったらすぐに教えてもらえるような環境があると、勉強量が一気に増えていきます。
この方法で、国語のテストが一気に20点ほどアップし、なんと最高得点をとることができました。
子供が勝手に勉強するようになった!

子供に口うるさいことは言いたくないし、だけど何も言わなかったら永遠に勉強しない、、
将来のために今勉強しといたほうがいいとわかっていても、なかなか行動できない、、
しかも相手は思春期で、親の言うことなんかまともに聞くわけもなく、この時期は腫れ物にさわるように子供の対応にも悩ましいものがあります。
親が思っている以上に、子供は自分の進路について不安を抱えているのです。
勉強をしたがらないというのは、不安から自分を守っているのかもしれません。
子供の不安な気持ちに寄り添い、不安を解消するための方法を一緒に模索する中で、親子の信頼関係も築かれていきます。
子供との信頼関係を築き親子二人三脚で受験に臨めたら、子どもの学力もぐんと伸びていきます。